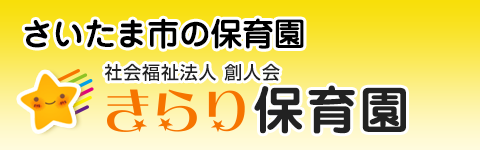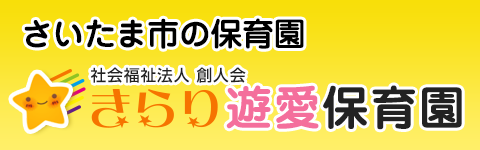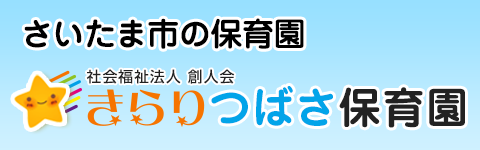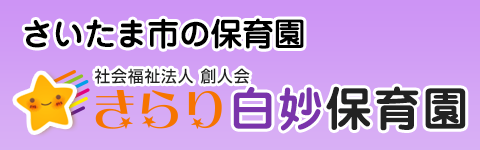ついに2345歳児による異年齢・縦割りで行ってきた遊びも最終回となりました。最終回はクリスマス会の当日です。自由に遊ぶのではなく、部屋の飾り付けとダンスを一緒に行なっていきます。全10回の遊びが子どもたちに与えたものは何なのか。それでは当日の様子をご覧ください。
♯10 (2歳児と3歳児と4歳児と5歳児)

長いシリーズとなりましたね
4クラスが勢揃い。今日で10回目なんですね。
今日はいつものように自由遊びではないこと、そして今日何をするのかを保育士から説明していきます。
まずはクリスマスの絵本を読み聞かせ、クリスマスの雰囲気を作っていきます。そのあとはみんなで会場を飾りつけていきます。

どこに何を貼るのも自由
前日に作っていたクリスマス飾りを2歳児3歳児4歳児で会場に設置していきます。わからないところは上の学年が教えてくれたり、一緒にやってくれていますね。
自然と下の年齢の子に優しくできる。それがこの9回にわたる遊びの中で子どもたちが学んだことの一つ。元々優しかったけど、さらにその傾向が強くなったような気がします。
本当にやってよかった。大変だったけど。

ツリーの飾り方も自由
その間に5歳児はクリスマスツリーを飾り付けます。
自由遊びがどういう展開を見せるか予想できなかったので、今日のクリスマス会の流れも内容も、前日の2345歳児合同遊びが終了してから保育士と園長で集まって決めています。
子どもの興味関心があるもので、教育的効果が高いもの、そして前日に急に準備できるもの。ハードルが高い保育計画となりましたが、保育士たちがうまくやってくれました。

歴史は繰り返すのか
いつもの2歳児がツリーを壊しにきたのかと身構える3歳児と5歳児。
しかし、彼がツリーを壊すことはなかった。学んでいるんです。昨日、みんなに受け入れられたから、もうわざと壊す必要なんてない。
しかも右には前日にツリーを倒した2歳児を抱っこして連れていく5歳児。同じミスは繰り返さないというみんなの強い意志を感じます。

協力して作り上げていく
ツリーの位置を中央に移動して、234歳児が飾りつけた白いパーテーションを合体して会場を作っていく。最後に輪飾りを4歳児と5歳児で設置します。
全部子どもたちで考えてやってもらいます。保育士は手伝いません。その分、思っていたより時間が押してしまいましたが、子どもたちが一生懸命やっているので急かすようなことはしません。元々の計画通り進めることが良いことじゃない。活動を通して子どもたちが何を学んでいるかが大事だからです。
計画はあくまで計画。子どものライブ感を大切にします。
そして何より、楽しいと思っているかが大事。みんな楽しそうなので、これで良いのです。

子どもの協力の結晶
完成したクリスマス会の会場。子どもだけで作ったにしてはカッコ良いと思いません?
やっぱりクリスマス会はツリーがあるのとないのでは違いますね。存在感がすごい。
そして部屋の中で一番存在感のあるものが、何度もみんなで作り直した「やり直し」のシンボルであるクリスマスツリーだということが素敵だなと思います。
自分たちの協力した思い出が形となって存在しているのです。

君、1人なのかい?
飾り付けが終わり、ダンスの時間。じゃんけん列車に入れない2歳児の女の子を見つける、2歳児の男の子。
後ろを振り向き私を見る男の子。優しく背中に触れる私。そのまま女の子の方へ向かう男の子。
そう、それでいい!

キターーーーーーー!!
自分から女の子の後ろにつき、列車になりました!
やったー!!
静かにテンションの上がる私。
自分から全体の遊びのルールを理解し、列車を作って遊びに入る「資格」を得る。しかも同じく1人だった2歳児を選んで。お互いにとって良い結果を作る。最高です。
そうだ。そうやって遊びに入るんだ。壊したり、邪魔なんてしなくて良い。それを学んでいるようです。

4歳児の覚醒の瞬間
同じく誰かと遊べない2歳児の女の子。それを4歳児の男の子がしっかりと手を握り、離れないように連結しながらみんなの輪の中に入っていきます。
異年齢の良さが出てますね。だけどそれ以上に何より君の良さが出てる。不器用だけど優しい。

見たことあるぞ、こういう展開
転んで泣く2歳児。誰かが来てくれるのを待っているので、また5分以上この状態。前と同じですね。
最初に気づき、そばに来たのは5歳児の男の子たち。いつも自分の遊びを優先していた子達が、こんな行動を見せるとは思っていませんでした。
異年齢での遊びが、この子達にも変化をもたらしているのかもしれません。

カーブを曲がりきれずに腕を回してバランスをとってます
5歳児が話をしても動かない2歳児の女の子。
それを見て、全力で駆け寄る4歳児の姿が。
誰よりも早く、あの子の元へ!

4歳児の皆さん、さすがです
そして集まる4歳児女子たち。こういう時に駆け寄るのはいつもこの子達ですね。
「転んじゃったの?」と左の女の子はいつものように言葉で気持ちを受け止める。
真ん中の子は優しい雰囲気で包み込む。
具体的に立たせようとする右の子。だけど無理には引っ張らない。立ち上がるきっかけだけを与えようとしている。
そして男の子は・・・。

小さい子に優しくできるのが成長の証
頭を優しく撫でる。前回、ぶつかって泣いていた時に頭を撫でてもらっていましたね。優しい行動は伝染していくのです。
いや、すごいな、この子達。こんな役割分担あります?
やってることが被らないんだもんなぁ。
それでも動かない2歳児の女の子。これでもダメなのか。
何が足りない?

台本があるみたいな展開で驚きます
次に走ってきたのは2歳児の男の子。しっかりと女の子の手首を掴み、一緒に歩き出す。
そうです。この手はおもちゃを奪うためでも、誰かを叩くためでもなく、優しく誰かの手を引くため。前回1人遊びの女の子を誘った時と同じように、その卓越した行動力と意志で一緒に歩いていきます。
足りなかったのは、一緒に歩いてくれる仲間。2歳児クラスの仲間だったのです。
このシーンだけでも、このプロジェクトが意味のあるものだったという証明になるのではないでしょうか。

端っこがないのが輪
学年を超えて手を繋ぎ、一つの輪になる。
「楽しいね」
見つめ合い、笑い合う。
1人の子はいない。みんな仲間なんだ。

最後の仕上げです
ただ1人を除いて。
輪に入らずに走り回るだけの2歳児。
みんな「おいでー」と声をかける。手を差し伸べてもダメ。
その足は止まらない。

これもすごくないですか?
彼が止まったのは唯一、ここでした。
それは前日に自分に本気で向き合ってくれた5歳児の女の子。
この子の声だけが男の子の心に届いたんです!
あれは無駄じゃなかったんだなぁ。
「一緒にやる?」
その言葉が届いたのか、この子の横の輪に一度入り、自分の居場所を確認するように周りを見渡す。
そしてまた走っていってしまいました。
惜しい!
あと少しだったな。だけどこれくらいが限界か。
私は男の子のそばにいき、優しく抱きしめる。

これで一つの輪が完成
そして「おいで」と言ってくれた3歳児の女の子の横にスッと誘導する。手を繋ぎ、輪の中に入ることができました。
「安心」を私が与えたことで、みんなの輪に入るという「挑戦」ができたのです。本当は子どもだけの力で乗り越えたかったけど、まだちょっと大人のサポートが必要なようです。
そして私がやり方を子どもたちの前で示すことは、見本になる。保育士に向けて見本を示しているのもあるけど、子どもたちに私のやり方をそれとなく見せているわけです。
無理強いはしない。子ども自身のやりたい気持ちを膨らませて、自分の意思で選ばせる。難しいけど、私たち大人も挑戦したいやり方です。

なぜカメラ目線?(ドヤ顔?)
面倒見が良く、優しく、行動力もある。そんな4歳児の2人の間に入れてもらう。涙を拭うのは本人。全てをやってあげるつもりはない。甘やかすのではない、ちょうど良い関わり方を4歳児がやっています。
大人も見習いましょう。私も見習います。

一体感と高揚感
最後のダンスはみんなノリノリで踊っています。
3歳児たち。この子たちの優しさ、頑張りがあっての2歳児の成長でした。君たちにお願いした私の目に狂いはなかった。
そして、君たち3歳児自身の成長もたくさん感じました。

あの時はありがとう
緊張が強く、活動に入れないことが多い中央の2歳児の女の子。誰かのために動けるのに、自分のためには勇気を出せない不思議な女の子。
横に寄り添うように立っているのは同じく2歳児。男の子と押し合いになった時に助けてくれた中央の子の笑顔を引き出す。あなたがダンスに入れないなら、私も入らない。そばにいる。
ダンスをしないでそばにいるのが仲間の印。素晴らしい。
そしてそれをサポートするのが保育士の腕の見せ所というわけです。
手前味噌で恐縮ですが、うちの園は園児もすごいけど、保育士もすごいんですよ。なんちゃって。

激しいダンスにカメラのピントも合わない
4歳児。5歳児の陰に隠れがちですが、さっきのように優しい行動ができるクラスです。そして喧嘩しても仲直りできるし、みんなで笑顔になることができる。
もうすぐこの子たちが年長さんになる。今からそれが私は楽しみです。
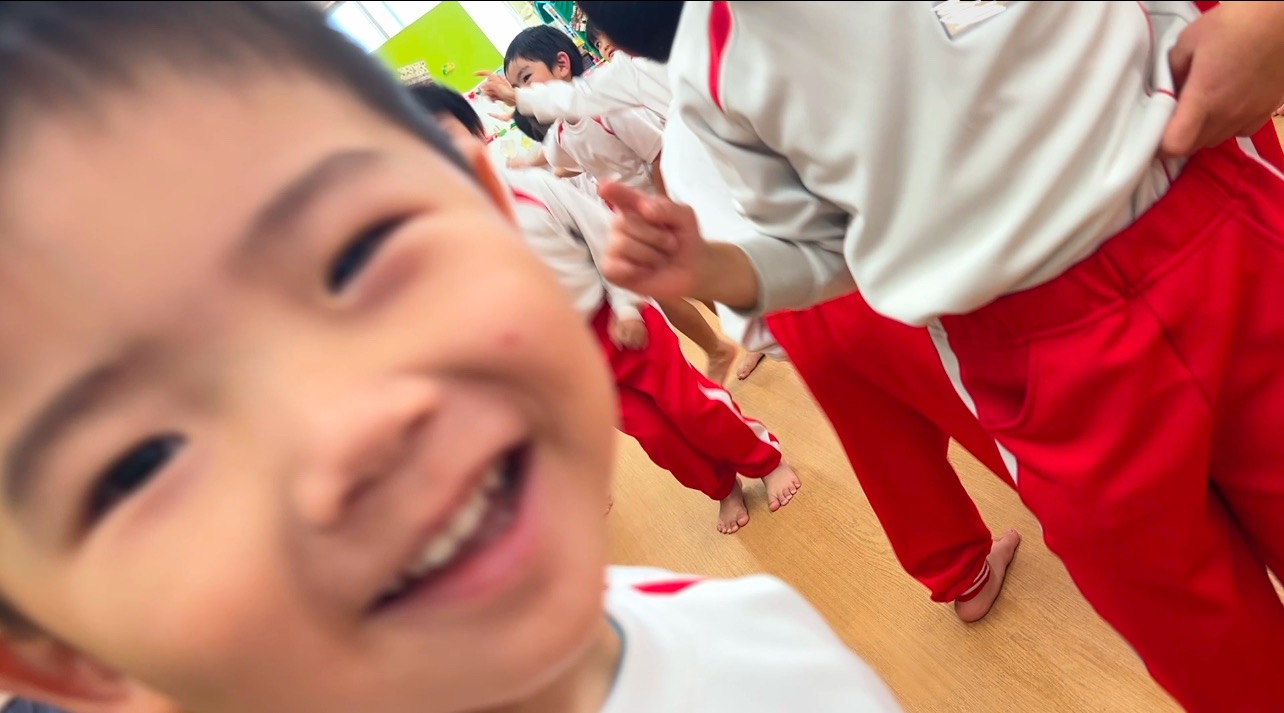
育ち合う子どもたち
ダンス終了間際、「楽しい?」と私が聞くとニコッと笑顔を見せてくれました。
そうだろう。君のことを嫌いな子なんてうちの園にはいないんだ。
みんなの邪魔をしなくても、誰かを押さなくても、きっと一緒に遊べる。「おいで」と呼び、手と繋ぎ、一緒に笑い合う。それができる仲間しかいないってことを体験できたはず。
これからの君の人生において、保育園で過ごす毎日がかけがえのない宝物になるように私たち保育士は全力を尽くすけど、きっともうすでに仲間たちが君にとっての宝物になってるんじゃないのかな。
君のおかげでみんないろんなことを考え、試し、成長することができた。君のおかげで様々なドラマが生まれた。ありがとう。
仲間と一緒に育ち合う。それがこの保育園の良いところなんです!
以上、2345歳児合同プロジェクトでした!
いやぁ、やっと完結しました。長かった。長さもそうだけど、内容がしんどかったですね。結末を知っているだけに、2歳児の激しい部分をどう表現するかには頭を悩ませました。
七夕まつりもお化け屋敷も長くなってしまったのに、まさかこのシリーズが一番長くなるとは思っていませんでした。人数が多すぎるのと、23歳児と45歳児の遊びが見えないところでどう繋がってくるのかを予測できなかったので、これまでのシリーズの倍以上の写真を撮影しています。数千枚の写真から、ストーリーを浮かび上がらせ、プロットを作り、写真を選抜、加工して、執筆する。膨大な時間がかかってしまいました。
だけど、それだけ良い物語になったんじゃないかと思います。
最後の回の解説をしておきます。
クリスマス会当日は、今までと同じように「ツリー壊し」「仲間に入れない」「泣いて復活できない」などの過去と同じような展開が起きそうになりました。実は、子どもの成長とはそういうものです。同じようなモチーフで課題が再現される。それを繰り返して少しずつ乗り越えていくんです。だから、最後にこれらが出てきたのは逆にすごく良いことです。これで完全に乗り越えたと言っても良い。
大人はまた同じことを子どもがしていると思い込みます。よく観察すると「前回より時間が短くなった」「前回より激しさが減った」などと良い方向に少しずつ変化しながら同じようなミスや問題となる行動を繰り返すものです。
もちろん繰り返しているのに良くならないという状況も存在します。だから、繰り返される事象が、良い意味なのか悪い意味なのかを見極めないといけない。子どもの育ちの評価というのは本当に難しい。
何も変わらないまま子どもたちに同じ課題が繰り返されているのなら、それは改善のために大人が知恵を出していかないといけません。放っておいても悪くなるだけです。
それから、全体を通しての補足を少し。
2歳児中心の物語にどうしてもなってしまいましたが、できるだけ全学年のエピソードも交えて書きました。だけど人数が多すぎて全員の動きを追って成長を解説するのは難しいので断念しました。登場回数に偏りが出てしまって申し訳ないなと思うのですが、それだけ全体に影響を与える子や、動きが出やすい子の登場回数が増えるのは仕方がないと思っています。
異年齢保育や縦割り保育というものにネガティブなイメージを持つ人が多いので、そうではないよという一例を示したかったのですが、私が思っていた以上に学年を超えて育ち合う良さが出る展開になりました。同学年の保育と異年齢の保育、どっちが良いというわけではなく、必要に応じて使い分けるのが良いかなと思っています。
また、今回のシリーズ全体を通して言いたいことの一つは、「どんな子でも育ち合うことができる保育がある」ということです。これを「インクルーシブ保育」と言います。子どもたちが深く関わり合いながら育ち合う。年齢、障害、性別、疾病、人種、文化、宗教などあらゆる違いを超えて育ち合う。それができる保育、教育です。国も世界も、今この方向で教育をしようとしています。
異年齢保育、縦割り保育の解説という形をとっていますが、本当に言いたかったのは「どんな子でも育ち合う保育環境」の紹介です。そしてそれを行うための保育士の心構えや判断のヒントを述べています。
多様性の時代を生きていく今の子どもたちに必要な保育、それが「インクルーシブ保育」なのです。
まぁ、そんな難しい話は置いておきましょう。今回も子どもたちは素晴らしい輝きを私たちに見せてくれました。
プロジェクト保育があまりにもうまくいくので、毎回やるのがプレッシャーになっているのが正直悩みどころです。こうやってブログにまとめるのも大変ですが、今後も頑張っていきたいと思います。
それでは、また新シリーズでお会いしましょう。読んでいただき、ありがとうございました!