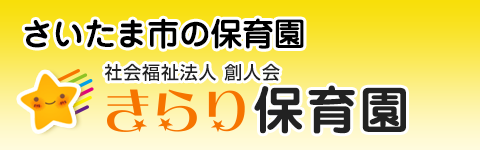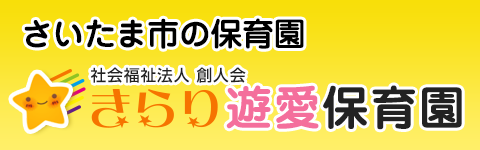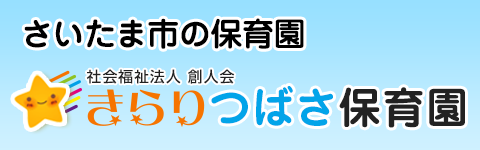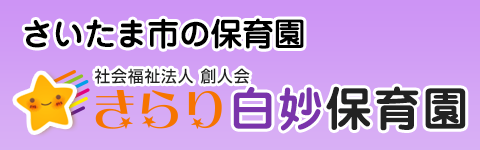2345歳児合同のプロジェクトも後半戦に突入です。保育士が何も言わなくてもクリスマス遊びになるのかを見ているわけですが、今のところ全くなりません。去年の遊園地プロジェクトの再現やごっこ遊びに夢中。まだ各自の遊びをバラバラに行うだけの4歳児5歳児の第4回の様子をご覧いただきます。
♯6 (4歳児と5歳児 第4回)

いつ見ても美しいスタートダッシュ
4歳児5歳児の第4回。相変わらずのスタートダッシュを決めていますね。おもちゃの所有権争いが起きやすい自由遊びでは最初に何を手に入れるかが重要になる。それを子どもたちはわかっている。
だけど、なんでもいいよと思っている子もいます。あるもので工夫して遊ぼうという子。そういう子は走りません。ゆっくり動いています。

マットを押す遊びが生まれる
中央の男の子が、滑り台のマットの上に乗ろうとしている女の子がいるのにマットを押しています。当然ですが、女の子たちから批判されてしまいました。
テンションが上がると人は行動を止めにくい。批判されても続けてしまい、また批判される。面白いとき、人はもっとやりたいと思うから止められなくなる。逆に言えば、こういう子は「面白い」って感じやすい子なんです。感動しやすい。夢中になりやすい。
夢中になった時に子どもは成長するから、伸び代がすごくあるってことです。
こういう子を伸ばすも伸ばさないのも、周囲の大人次第だと思います。

優しさってなんだろう
批判されて泣いたところを同じ4歳児の女の子に慰められる。そして、どうすれば良かったのかを教えてもらう。
4歳児クラス、泣いて誰かの気を引くってのが常態化してきますね。これは優しい子が多いから起こる現象です。泣くと誰かが来てくれて優しくしてくれる。そういう体験を繰り返す毎日だから、泣いたほうが得になってしまう。
マットの上に座っているけど背を向けている女の子がいますね。この子は以前もマットに乗れずに泣いている子がいるときにみんなで乗せてあげて記念写真を撮った時に1人だけ笑顔じゃなかった。
泣けば良いっていう今の状況がおかしいと気付いているからです。優しくすることが必ずしもその子のためにならないってことをなんとなく分かっている。
本当の優しさってなんだろう。子どもたちが私たち大人に問いかけてきます。泣いた子に駆け寄るのが優しさなのか、あえて無視するのが優しさなのか。
答えは出ないまま、遊びは進んでいく。

閉じた世界
流れに乗れない5歳児女子たち。奥の3人はみんなと離れて自分たちだけの世界で遊ぼうとしています。黄色いマットを中心に集めていますね。3人とも遊びを作り出していくタイプではないので、以前やったことがあることを再現しようとしています。家を作るとか、絵本屋さんの準備をするとか、コインや丸を集めるとか。
でもそれってもう古いんです。ブームは去っている。誰も面白いとは思わない。だから誰もこっちに来ることはありません。
遊びってナマモノなんですよ。旬がある。ブームには賞味期限がある。それを理解できない場合、集団の波に乗れない。
手前の子は前回同様に「何も面白い遊具を手に入れることができなかった」状態です。自然発生的に誰かと遊ぶのは好きだけど、「約束をした子とだけ遊ぶ」っていうのが好きじゃない。だったら1人が良い。そうなってしまう。前にも言いましたが、オープンマインドは孤独になる。

前回の遊びの再現が続く
こちらも前回同様、緑を「資格」にして繋がる5歳児男子たち。右の2人はマットを不安定な状態にして歩き、転ぶのを笑うという遊びです。
一番奥はお化け屋敷のゴミ箱お化けの再現ですね。緑の箱に自分が入る。
中央の5歳児女の子2人は2人の世界、そして後方の4歳児女子は真似をしている。歌いながら踊っています。

仲間に入れてもらえれば押す行為をすることはない
先程マットを押して批判された男の子も仲間に入れてもらえました。その代わり、マットから降りる手前の女子2人。定員数があるから、誰かを入れると誰かが降りることになる。あえて自分が降りるという選択をした2人。他者を尊重する気持ちが育っています。

遊べない子が集まる窓辺
前回の不安定なマットの上に立って窓の外を見る遊び。こちらも引き続き行われています。前回の再現が多い回ですが、それだけ前回の遊びが楽しかったということです。現実世界では土日を挟んで数日経っていますが、子どもの世界ではハッキリと繋がっています。

そういうのじゃないから(笑)
手前の男の子が前回のように追いかけっこをしたくて恐竜になって襲いかかっていますが、相手の男の子は「あ、ごめん。今そういうのじゃないから」と大人みたいな返しで笑顔で断りました。
断った方は、男子2人でマットの上を歩いて転ぶ遊びに夢中。2人の世界で遊んでいるため、誰も入ることはできません。夢中になると視野が狭くなる。周囲の子の気持ちが見えなくなるんです。

クリスマスカラーの家
拒否された右の男の子、遊ぶ相手がいない右の女の子、そして5歳児男の子2人の遊びには入れなかった2人が集まって、何かを作り始めました。家のようです。
赤と緑でクリスマスカラーになっています!
自然とクリスマスの遊びになるのかを裏のテーマとしていましたが、第4回でその兆しが見えてきましたね。ワクワクします。部屋の反対側の5歳児女子3人が黄色のマットを独占したために、赤と緑しか手元になかった。その結果、クリスマスを連想させる建造物を作ることになった。
偶然の積み重ねが物語を作っていきます。

新しいアトラクションを女子が作り出す
中央で2人きりで遊んでいた5歳児女子。バランス遊具を横にして、平均台のように上を歩く遊びを始めました。それを見て集まってくる4歳児女子。それを受け入れてみんなで遊ぶ。
2人の世界からの脱却。閉じた世界から、開かれた世界へ。
ゆりかごにしていたバランス遊具を組み合わせて遊ぶという判断ですが、みんなでシェアした方が楽しいと思ったということだけでなく、取られることがないと信頼しているからです。

優しさってなんだろう2
手前はその輪に入りそびれた4歳児女子。なんか毎回、こうなってますね。いじけるというか、誰かが来てくれるのを待つパターンになっている。あまり良いことじゃない。泣くと誰かが優しくしてくれるというパターン。
だけどその様子を見て考え込む5歳児の男の子。さっき、自分が遊びに入れなかった経験をしているので、気持ちがわかるのです。マットを折りたたんで、女の子の手を優しく挟む。
それが面白くて笑顔になる女の子。
優しくするのでもなく、無視するのでもなく、笑顔にする。第3の選択肢を示しています。すごいですね。私たち大人も、こういう柔軟な思考と表現ができるようになりたいものです。
さて、ここでもう一つ動きが。中央のマットで遊ぶ2人が5歳児男子の憧れなので、他の5歳児男子が中央に向かってクリスマスカラーの家を運んでいます。

胎児の丸まりは赤ちゃん返りの証拠
開始直後に泣いていた男の子に声をかけていた4歳児女子が、泣いている子を見つけて、またしても声をかける。
初回では黄色い丸を「資格」にして他の人を寄せ付けない遊び方でしたが、今日は積極的に関わっていますね。優しい子に育っているのは良いことだけど、ちょっと気になることがあります。
誰かが傷ついた時に声をかけるということは、自分が傷ついた時にも誰かに声をかけてほしいと思っている子だということです。この子が涙する時、周囲の子たちはどうするのか。ちゃんと来てくれるのか。「自分ばっかり頑張ってる」という感覚にならないかが心配です。
優しい子が損をする世界にはなってほしくない。少なくとも保育園の中では。

遊びで繋がる仲間関係
バラバラに遊んでいた5歳児男子。クリスマスカラーの家をマットの近くに持ってきたことで遊ぶ場所が近くなり、みんなで遊ぶ展開になりました。2人が作ったコースを実際に体験する。そして失敗して転んで笑う。笑い合う。
実は「失敗する」ことを面白がる遊びなんですよ。転んで笑い合うってことは。
つまり「しっぱいしたっていいんだよ」ってことです。
お化け屋敷プロジェクトからの繋がりを感じます。遊びって繋がっているんです。大人がそれを見えていないだけで。

つまらないって顔に書いてありますよね
相変わらず3人で家を作っていますが、楽しくない。立っている子はずっと休みだったので、この環境での遊びがよくわかっていない。本当は盛り上がっている向こうで遊びたいけど2人に「一緒に遊ぼう」と言われているので裏切れない。
本当につまらなそうな3人。ここだけ空気が澱んでいる。
実は5歳児女子だけ、日常でも「〇〇ちゃん、今日の〇〇の時間一緒に遊ぼう」と先に予約を取って、予約をしていない子とは絶対に遊ばないという変な習慣が身についてしまっていたんです。「閉じた関係で人は安心する」ということは何度か説明しましたよね。遊びたい遊びをするのではなく、誰と遊ぶかが先に決まり、やりたくもない遊びで時間を潰す。良いことではない。
私はそれを変えたい。そんな約束なんてくだらないとそう思える体験になってほしい。プロジェクトの中で「みんなで遊ぶ方が楽しい」という体験で「〇〇ちゃんと遊ぶから、あなたとは遊ばない」という価値観と習慣を塗り替えたい。

ふて寝ってやつです
つまらなそうな3人の反対側、こちらも1人で寝っ転がる5歳児女子。みんなの盛り上がりを見て、逆に気持ちが冷めていく。

よく見ているなと思いました
泣いている女の子を笑わせるため体を張る5歳児。滑り台状にしたマットの上に寝て、4歳児男子たちを邪魔し、自分を押させてマットから落ちることで笑いをとる。
自分から直接的に関わらず、空間を活用して他の子の意欲と関わりと笑顔を引き出すやり方。これはもう完全に私ですね。私の技を5歳児がやってみせています。なんでできるんだろう。保育士でも難しいのに。これには感動しました。なんていうか、嬉しかった。

お昼寝タイム
平均台の上を歩く遊びもひと段落した頃、手前で寝ている5歳児の真似をするように4歳児女子たちが一斉に寝っころがり始めました。
何もせず、寝るという状態が仲間の印、それが「資格」となる。
気づきましたか?
前回のラストで3歳児たちがたどり着いた「何もしない遊び」「みんなで寝る遊び」による気持ちの共有と同じです。
遊び方じゃない。遊具でもない。存在するそれだけで仲間なんだ。そういう境地。
人と時間が違うのに、全く同じことが起きていく。遊びって面白い。

落とす遊び
わざとマットから落とす子、落とされないようにする子。役割が分かれての遊びが始まりました。これは冒頭で、マットを押して批判された4歳児の模倣の遊びになっています。あの時はマットを押すのは不適切だったけど、今はそれを遊びに昇華してしまっています。
遊びは、そのものの価値を180度変えることもできる。冒頭の4歳児の一部始終を見ていた5歳児だからできた遊びです。
不適切な行動は子どもたちに影響を与える。真似てしまう子も出てくる。だから、似たような行動だけど、適切な形に変換して真似をするようになるのが理想です。今回のように。そういう工夫ができる子を育てています。

ベビーが大量発生
寝っ転がるだけでなく、そこに意味付けがされていく。大量の赤ちゃんが発生することになりました。ここにきて、赤ちゃんごっこが集団で展開されているのです。
第2回でお母さん1人が赤ちゃん1人の世話をしていました。第3回ではお母さん1人が赤ちゃん2人の世話をしていましたね。そして今日の第4回、大量の赤ちゃんを世話するお母さんが誕生したのです。お母さん、ぐんぐん成長しています。

そばにいるよ
遊びに入れず寝ている5歳児に寝ながら近づいてく4歳児3人。輪投げ屋さんにしてもマットの上に誰かが乗れない時にしても自分たちを助けてくれた5歳児に寄り添っていく。
近くにいるだけで仲間になる。寝ている子の横で自分たちが寝ることで、同じ遊びをしていることになる。
孤独な心が温かさで満たされていく。

マジで空気が重い
面白くない3人。右手前の子の指示で家を作っていますが、全然うまくいかない。というか、なんでこれを作っているのかもわからないし、興味もない。時間だけが過ぎていく。
マット不安定転ぶ遊び、マットの上から落とす遊び、大量の赤ちゃんごっこ。部屋の中では集団で大盛り上がりしているのに、自分たちだけが面白くない。

心の解放は心の交流から
今日のお母さんは来た子を拒まない。すべての赤ちゃんを受け入れています。あの日、赤ちゃんになりたい子を押して拒否したなんて信じられないくらいの心の開き方ですね。
以前は人を選抜していた子が今日はオープンマインドの心持ちになっています。それはなぜか。前回、オープンマインドの子(今日はずっと寝ている)と2人で濃密な時間を過ごしていましたね。深い心の交流をすると、相手の核となる部分を取り込むんです。無意識に影響し合う。
誰かの良いところは、遊びを通して誰かの良いところになる。

1時間越しの復活
1時間近く寝ていましたが、自分の寝ていたマットを布団にして赤ちゃんにかけてあげました。ついに復活です。前回あまり乗り気じゃなかった、ごっこ遊びに自分から入っていきます。
1人では復活できなかった。近くまで来て一緒に寝てくれた4歳児の女の子たち。そして覚醒したお母さん。みんなの支えで復活できた。

わからない時は邪魔をするしかないという悲しさ
大量の赤ちゃんごっこに入れてもらえた右の男の子。初回からずっと一緒に遊びたかった女の子と接触する機会が持てました。あの時は遊びの邪魔をすることで接触しようとして失敗しています。
だけど今回も、女の子が欲しい丸を背中に隠して渡さないという行動に出てしまっている。今の遊びでは、丸を交換するのが「資格」となることはわかっているけど、どういうタイミングでどのように遊べば良いかまではわからない。だから、初回と同じように「邪魔をする」という行動に出てしまっているのです。
怒って去っていく女の子。そりゃそうだ。
そしてまた考える。何がいけなかったのかを。
失敗して学ぼう。これを意味のある失敗にしていこう。

落とす遊びは高度になっていく
滑り台のマットから落ちないようにする遊びの4歳児たち。前後を5歳児の男の子が挟んでいます。学年を超えて遊んでいます。遊んでいるというか、遊んであげているというか。
異年齢の遊びだと、こういう展開になることがある。良いですね。

視察は空振り
つまらない5歳児3人は、たまに部屋中をうろうろしてみんなの様子を見ています。他の子の遊びに参加しようという動きを見せると他の2人から非難される。だから3人に戻る。それの繰り返し。他の子たちと関わりたいのにお互いに足を引っ張り合う。
主体的でもないし、対話もないし、深い学びもない。自由遊びというのは、こういうふうになる危険性があるんです。子どもたちがやりたいことをやってれば成長するわけじゃない。成長を妨げ合うこともある。
だから、私の考えはこうです。今日は「つまらない」という経験をしてもらおう。そうすれば、次回は別の遊び方になるはず。助けるようなことはしません。心の底からつまらないと思うのも学びだからです。

自然と助ける兄貴
第一回の時と同じように、女の子とうまくいかない後には5歳児の男の子のところへ行く4歳児の男の子。棚の下に入り込んでしまった丸を5歳児が取ってあげています。兄貴分って感じでしょうか。同年齢と遊ぶだけでなく、上の子に遊んでもらう体験も、この子にとって必要なことです。遊び方を学び、コミュニケーションを学ぶ機会になります。

やっぱり男だけで遊ぶって最高だよな!
こうやって5歳児の男の子たちの遊びに入れてもらう。笑顔になりました。
もしかしたら女子と遊ぶのは違うのかもしれない。そろそろ気付いてきたんじゃないでしょうか。女子の遊びは複雑で、男子の遊びはルールがわかりやすい。ルールの把握が難しい子は男の子たちとバカやっている方がうまくいく。

「つまらない」の代償
何にもならないまま1時間15分経過。右の子が青い丸を身につけたところ、左の子も同じ青い丸を身につけました。
「ねぇ、真似しないで」
拒否されてショックを受ける左の子。これが仲間の「資格」だと思って一緒に身につけたのに、それを拒否されるということは仲間じゃないということ。酷い話です。イライラをぶつけ合う関係になっている。
それだけ、今日はつまらなかった。遊ぶメンバーを固定したことで上手くいかなかったんだという経験をした。

傷つけ合いたくないのに
ショックを受けて青い丸を捨てる左の子。
言ってしまったことに自分自身もショックを受ける右の子。
そのやりとりを見て静かに黄色い丸を身につける中央のゆりかごに乗っている子。

人間だもの
声をかけて同じように黄色い丸を身につける2人。そして右の子は青い丸を身につける。
そして3人でゆりかごに乗る。色が違うけど、丸を身につけて。全く同じにならなくても良い。みんな違ってみんな良い。「同じ」が嫌な気分の時もある。ただ、笑い合いたいだけ。仲良くしたいだけ。3人の気持ちが一つになる。
今日初めての笑顔は終了の1分前でした。今日の経験が、きっと明日以降の何かを変える。意味のないことなんてない。全て繋がっているのだから。
以上、4歳児5歳児の第4回の様子でした。最後に3人も笑顔になってホッとしました。つまらない時間を過ごすのも学びだと言いましたが、やっぱり子どもたちには笑顔になってほしいですからね。
最後の「同じ」が嫌な気分の時もある、というところ。ここって深いなと思いました。大人はいつも「みんなで仲良く遊びましょう」と子どもに言う。「仲間に入れてあげて」「貸してあげて」など、それがさも当然であり、間違いのはずがないという顔で子どもに指摘する。
本当にそうなのでしょうか?
この子と遊びたくないと思っていても遊ばないといけないのでしょうか。仲良く遊べない子はダメなのでしょうか。
難しい問題です。
例えば「多様性を認めましょう」と言いながら「多様性を認めないという意見を認めない」という人がいます。矛盾しています。「平和のために戦う」とかもそうですね。
みんな同じ気持ちになって仲良く一緒の目的に向かって動くのが理想ではあるけど、それが絶対だと保育士が押し付けてはいけない。みんなの輪に入らない子をマイナスに評価してはいけないんじゃないかと私は思います。
あくまでも子どもたち自身が自分の気持ちに正直になった結果「みんなで遊ぶ」になるのを待つ。それが大切なことです。押し付けはいけないけど、期待はする。「願う」とか「祈る」に近い気持ちで子どもの遊びを見ていく。
その先に、もしかしたら私たちが望む「未来」があるのかもしれないなと思っています。
そして、次回、4歳児5歳児たちにその時が訪れるのです!